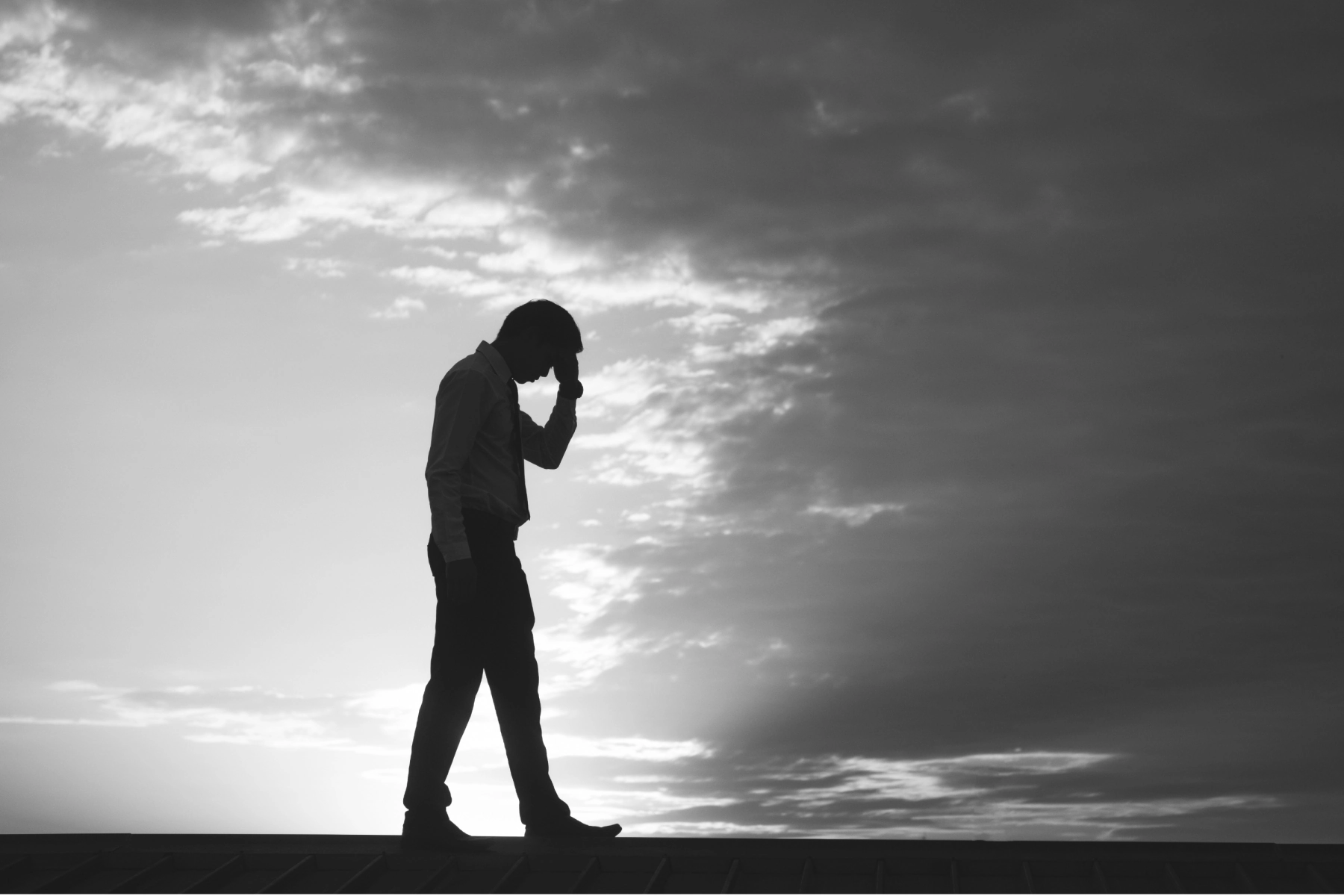Keep It Simple, Stupid.
“KISSの法則”をモットーにしているが、ここで大事なのは「複雑なものをシンプルに捉える」ことであって、単にシンプルであること自体には、ほとんど価値がない。
物事は、基本的に複雑だ。
MECEという言葉もあるが、あれだって“MECEに構造をつくること”に価値があるのであって、この世にMECEな事象そのものが存在するわけではない。
世の中、そんな単純じゃねぇよ、である。
ここを履き違えると、
“複雑なものをシンプルに、シンプルなものはそのまま”
という浅い整理に陥る。
それでは表面だけをなぞることになり、面白くもなければ、価値もない。
どんな事でも、背景があり、物語がある。
そのあるもの・ないもの、見えるもの・見えないものをこねくり回し、
いろんな角度から眺めながら、そこに一筋の切り口を見つける。
この作業をひたすら繰り返していくと、
複雑な世界が、ある時スッと一本の線として立ち上がる瞬間がある。
その瞬間こそが、意味の解像度が上がるということだ。
「シンプルにすべし」は本質だ。
だがそのプロセスは、いつだってカオスである。